設計施工一括方式(DB方式)とは? メリット・デメリットと解決策
2024.07.25 Thu
建築・建設の基礎知識
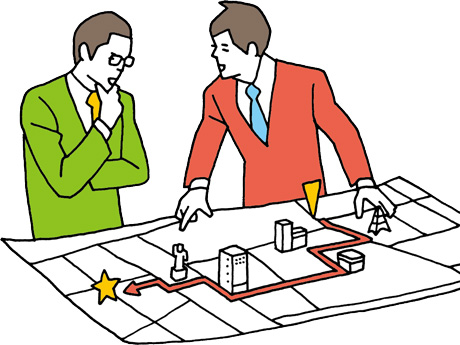
「設計・施工一括発注方式(DB方式)」は、建設プロジェクトの進め方の一つです。設計・施工を一つの施工会社に発注するこの方式は「工事品質の向上」「コスト変動の低減」いったメリットが期待できる一方で、事前に把握しておくべきデメリットも存在します。
今回は、建設プロジェクトにおける設計・施工一括発注方式の概要、メリット、デメリットについて詳しく解説します。また、デメリットを解消するための方法についても触れますので、ぜひ参考にしてください。
設計・施工一括発注方式(DB方式)とは
設計・施工一括発注方式とは、設計・施工の両方を一括して同じ会社発注する方式のことで、「デザインビルド方式」「DB方式(Design–Build方式)」とも呼ばれています。
一方、設計と施工を別々の会社に発注する方式は「設計・施工分離発注方式」です。
建設プロジェクトの設計段階は「基本設計」「実施設計」の2つの段階に分けられます。
・基本設計:施主の要望に基づき、建物の外観、内装、機能、仕様などを決定して基本設計図書を作成します。
・実施設計:基本設計を基に、工事の発注や行政へ申請を行うための詳細な図面や仕様などを記載した実施設計図書を作成します。実施設計図書が工事の発注図書となります。
設計・施工一括発注方式は、基本設計から建設会社に任せるケースと、実施設計から建設会社に任せるケースの大きく2種類があります。
1)基本設計からの設計・施工一括発注方式
基本設計から施工までを建設会社にまとめて発注する場合、一つの建設会社に設計・施工の責任を一元化でき、設計段階から施工段階へ移る際の工事発注先の選定の手間も省けます。また、基本設計の段階から建設会社の意見やノウハウが反映できるため、全体工期の短縮に期待できます。
2)実施設計からの設計・施工一括発注方式
基本設計を設計事務所に依頼し、実施設計から施工にかけて建設会社に依頼する方法です。建物のデザインや計画に高い専門性を持つ設計事務所などに依頼することで、発注者の要望が反映された設計内容で実施設計以降の段階に進められるメリットがあります。
設計・施工一括発注方式(DB方式)のメリット
設計・施工一括発注方式を採用した場合のメリットを3つ紹介します。
1)コスト変動のリスクを低減できる
設計・施工を一括して建設会社に依頼する場合、設計段階から実際に施工する建設会社がコストを確認しながら進めることができるため、工事段階でコストが変動するリスクを低減できます。
一方、設計・施工分離発注方式で進めた場合は、工事発注段階ではじめて施工会社に見積もりを依頼することになるため、設計段階からコストが変動する可能性があります。もし予算オーバーの場合は減額のために設計変更や追加予算の検討が必要になります。
2)全体工期短縮につながる
設計段階から建設会社に任せることで、全体工期の短縮が期待できます。建設会社は、設計段階から自社の施工技術や特許技術を活用し、現場条件や建物の特性に適した施工方法や仮設計画を検討しながら設計を進めます。
設計段階から施工段階への移行においても、施工会社の選定が不要となり、工期短縮につながります。また、工事に必要な資材や建設機械などを先行発注できる点も、工期短縮に寄与します。
3)建設会社の技術・ノウハウによる品質確保ができる
設計・施工一括発注方式では、設計から施工まで一貫して建設会社(ゼネコンなど)の高度な施工技術や豊富なノウハウを活用でき、品質の確保が可能です。施工精度が求められる建物や、難しい現場条件においても、施工者の技術を最大限に活用した設計が可能です。また、設計の意図が施工段階までスムーズに引き継がれることで、品質確保につながります。
4)責任の所在が明確化
設計と施工を別会社に依頼する場合、問題やトラブルが発生した際に責任の所在が不明確になることがあります。しかし、設計・施工一括発注方式では、設計と施工の両方の責任が一つの建設会社に集約されます。これにより、責任の所在が明確になり、迅速な問題解決を図れます。また責任の所在が明確になることは発注者が安心してプロジェクトを進められるポイントになります。
設計・施工一括発注方式(DB方式)のデメリット
設計・施工一括発注方式の持つデメリットについても確認しておきましょう。
1)工事費の妥当性の見極めが難しい
設計・施工一括発注方式の場合は、設計段階から一つの建設会社に一任するため、工事費の比較検証ができません。そのため、費用の妥当性を見極めることが難しくなる傾向にあります。
一方、設計・施工分離発注方式では、施工者を選定する段階で複数の施工者に見積もりを依頼することで、比較できます。選定に時間を要しますが、選定段階で見積もりの金額や内容を確認して、その妥当性を検証することで、発注者が納得できる工事発注になります。
2)発注者にもチェックする知識が必要となる
一つの建設会社に設計と施工をまとめて発注する設計・施工一括発注方式では、発注者にも「施工者の視点に偏った設計内容になっていないか」や「コストの妥当性」「求める品質が確保されているか」などをチェックする知識が求められます。
また、設計・施工を依頼する建設会社を選定する段階でも、発注者が適切な委託先を判断する必要があります。適性の高い建設会社を選定するためには、建物の特性やデザイン性、コスト、実績など、幅広い視点から発注者が見極めなければなりません。発注者側にも専門的な知識が求められるでしょう。
設計・施工一括発注方式のデメリットを解消するコンストラクション・マネジメント
設計・施工一括発注方式を進める上で、デメリットや不安を解消しながら発注者が安心してプロジェクトを進行するためには、コンストラクション・マネジメント(CM)の活用が有効です。コンストラクション・マネジメントは、発注者の立場で建設プロジェクトをサポートするサービスであり、発注方式や依頼先の選定などを支援します。
例えば、当社が提供するコンストラクション・マネジメントでは、事業構想・企画・計画から設計・発注・施工・維持管理において、プロジェクト運営、品質管理、コスト管理、スケジュール管理などの相談が可能です。設計・施工一括発注方式を希望される場合は、発注者の要望とプロジェクトの特性に適した設計・施工者の選定支援や、設計図書や見積書の確認、工事段階の支援など、発注者の意図する方向に進むように支援を行います。
設計・施工を一括して施工会社に依頼する設計・施工一括発注方式には、メリット・デメリットがあります。工事品質の向上やコスト変動の低減いったメリットが期待できる一方で、工事費の透明性の確保や、品質管理のチェックが発注者に求められるなど、デメリットもあります。デメリットを解消しながら、設計・施工一括発注方式の持つメリットを最大限に生かした建設プロジェクトを進めていきたい場合は、コンストラクション・マネジメントの導入を検討してみてはいかがでしょうか。
コンストラクション・マネジメントについては「コンストラクション・マネジメントとは?意味や概要をわかりやすく解説」にて詳しく解説しています。ぜひ併せてご参照ください。
その他、建物・不動産に関する各種ご相談は、日建設計コンストラクション・マネジメント(NCM)までお気軽にご相談ください。



